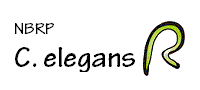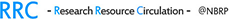| 重要なお知らせ |
|---|
|
令和5年7月以降の受付分につきましては、国内の株の手数料を変更いたします。
|
| 重要なお知らせ |
|---|
| 送付用の寒天培地には動物用のpeptoneの使用を中止し、大豆由来の製品を使用しています。 |
ナショナルバイオリソースプロジェクト「実験動物 線虫」
プロジェクトの目的
平成14年度より、文部科学省委託事業「ナショナルバイオリソースプロジェクト」がスタートしました。その中で、実験動物「線虫」も1つの課題として採択されました。線虫C. elegans は、生命科学研究における良いモデル動物です。ゲノムやESTの情報によって、存在するほぼ全ての遺伝子が明らかになっています(Science 282, 2012-2018, 1998)。その後、平成28年度より、本プロジェクトは日本医療本プロジェクトの課題に移管されて現在に至っています。その間、一貫して、本プロジェクトでは線虫に関わるバイオリソースを整備することにより、線虫を用いたライフサイエンス研究の推進をはかる、という目的で研究者コミュニティーのアドバイスを受けつつ、実施研究機関(東京女子医科大学)にて、事業を推進しています。主な事業内容としましては、バイオインフォマティクスによる線虫の遺伝子構造を基礎に線虫変異体の収集・保存・提供を行うことを目的としています。
このほかに、本プロジェクトでは、Cre recombinaseのトランスジェニック株やバランサー株の提供も行っています。
線虫株を用いた遺伝子機能解析
遺伝子構造の情報を利用して、興味のある遺伝子に欠失のある変異体を分離することは、線虫を用いた研究を行う上で有益です。線虫の欠失変異体を用いることにより、遺伝学的解析や生化学的解析を行い、多細胞生物の生命現象に潜む分子メカニズムに関する知見を得ることが可能です。変異体の表現型を記載することで、当該遺伝子が線虫内でどのように働いているかを記載することができます。一度、表現型が記載されると、変異体は一般的な遺伝学的解析にも有用性が増します。変異体の表現型を減弱させたり、増強させたりする変異体を順遺伝学的に分離することで、遺伝学的経路を見いだすことが可能です。 一方、微妙な表現型の解析を行いたい場合には、興味のある細胞で発現している遺伝子の欠失変異体の統計的な表現型記載を行うことにより、順遺伝学でスクリーニングするのが 膨大な労力を要する場合でも、遺伝学的な解析が可能になる可能性があります。発現パターンや遺伝子構造の情報を利用することで、系統的に二重変異体を作出し、冗長的な遺伝子機能への理解をすることも可能です。
変異体の表現型が記載されると、トランスジェニックレスキューを用いた解析にも有用です。野生型DNAやそれに変異導入したDNAを用いてトランスジェニックレスキューを試みることにより、それらの産物が線虫内で機能的であるかどうかを検定することが可能です。さらに拡大し、適当なタグを付加するとか、他の生物のドメインで置換するなどを施したDNAを導入することも可能です。このような実験により、蛋白質の構造-機能相関の解析や、分子間相互作用の解析などを行うことが可能です。染色体外のトランスジーンは、線虫内でのモザイク解析にも有効であり、遺伝子産物の機能する場所に関する知見を得ることも可能です。
もし、容易に表現型が見つからない場合でも、二次元電気泳動やトランスクリプトーム解析などを用いた生化学的な変化を調べることで、目的の蛋白質の機能の理解に役立つこともあり得ます。変異体解析の応用は、線虫を用いる研究者の努力により、さらに広く、深くなることが期待されます。解析の具体例を記載しておりますので、参考にしてくださいMitani, Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2017;93(8):561-577.。
運営委員会
本プロジェクトが研究者コミュニティーの研究の発展のために最適化されるべく、研究者コミュニティーより運営委員を選び、多角的なアドバイスを受けています。以下は、2022年4月時点での構成員(敬称略)です。
| 木村 幸太郎 | (名古屋市立大学 総合生命理学部) |
| 齋藤 都暁 | (情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 無脊椎動物遺伝研究室) |
| 佐藤 美由紀 | (群馬大学 生体調節研究所) |
| 澤 斉 | (情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 多細胞構築研究室) |
| 杉本 亜砂子 | (委員長、東北大学 大学院生命科学研究科) |
| 武石 明佳 | (理化学研究所 多感覚統合神経回路理研白眉研究チーム) |
| 中台 枝里子 | (大阪公立大学 生活科学部) |
| 中村 太郎 | (大阪公立大学 理学部生物学科) |
| 三谷 昌平 | (代表機関課題管理者、東京女子医科大学 医学部) |
実施研究機関連絡先
分譲承諾書等は、下記へ送付ください。
東京都新宿区河田町8-1
東京女子医科大学 医学部 生理学講座(分子細胞生理学分野)
NBRP線虫
E-mail: yoshina@twmu.ac.jp
分離済み変異体の分譲申し込み
- 本データベースに記載されている変異体株は、どなたでも分譲依頼可能です。ただし、多数の変異体を扱いますので、表現型解析などに関する個別アドバイスを行うことはできませんので、各々の研究目的や手法を熟考の上、申し込んでください。
- 今現在、分譲はアカデミック目的に限定しています。また、本プロジェクトから分譲された変異体を用いて、特許申請を行うことはできません。そのような場合には、大学事務局と契約書を交わしていただきますので、予め中核機関宛にご連絡ください。
- クレジットカード等でお支払い後に郵送します。