オオムギ種子分散システムの進化と栽培化起源地
小松田 隆夫
(農業生物資源研究所 農業生物先端ゲノム研究センター
作物ゲノム研究ユニット 上級研究員)
野生オオムギの実が成熟して散らばることは、自生地を拡大するうえで大事な性質です。しかし、ヒトの観点からすると実が成熟して収穫する際に落ちてしまうと収量は少なくなります。人類は収集した野生オオムギの中に実の落ちない突然変異が起きた植物があるのを見つけて、これを植えると一回の作業で実をたくさん収穫できることを発見しました。このようなオオムギを発見して栽培したことが“人類最古の農業”の始まりだと考えられています。いったいオオムギはどこでいつ頃栽培化されたのでしょうか。
イスラエルやシリア、トルコ、イラク、イランなどいわゆる「肥沃な三日月地帯」の有史以前の遺跡には、土器や泥の中にオオムギの炭化種子がみつかっています。野生オオムギを集めて食用とすることは2万3千年以上前にすでに行われていたことが遺跡の調査から分かっていました。野生オオムギからの栽培型オオムギの出現は炭素年代測定により1万年前ころと推定されています。しかしオオムギがどこで栽培化が開始されたのか明確な答えはありませんでした。そもそも栽培化は一回だけだったのでしょうか、それとも複数回あったのでしょうか。
これまで、岡山大学では野生オオムギの穀粒が落ちることに必須な2つの遺伝子(Btr1とBtr2)の存在を60年以上前から研究しています。この二つの遺伝子は密接に連鎖しています。
|
穀粒実が落ちることに関わる
遺伝子Btr1とBtr2の生物的機能 |
野生オオムギでは実が成熟すると穂の軸の節々の連結がはずれてバラバラになります(図1)。これまで本現象は、木々の葉や果実が成熟して自然に落ちる際に作られる「離層」と同じ仕組みによると長く信じられていました。離層では成熟とともに細胞間の接着物質が徐々に分解されることによって細胞と細胞が自然に乖離し、木々の葉や果実が、そしてイネや麦類の一部では穀粒が母体から脱落します。しかし今回、実際はオオムギではこのような離層が作られず、その代わりに穂の軸の節々で細胞壁の二次層、三次層が形成されないため細胞壁が極端に薄くもろくなることを発見しました。薄い細胞壁が乾燥によって物性の変化を生じ、さらに風や重力、動物が触れることなどによって細胞壁がくだけ、穀粒が落ちることが分かりました。したがって、2つの遺伝子は穂の軸の節で働いて、細胞壁を薄くもろくする役割があるといえます(図2)。 |
| |

図1. 野生オオムギの種子脱落の様子 (文献1) |
|
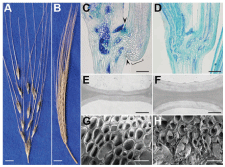
図2. 細胞壁が脆弱化する事による小穂脱落。A, C, E, Gは野生オオムギの成熟穂、穂軸節の縦断面、同透過型電子顕微鏡図、同透過型電子顕微鏡図による観察像。B,D,F,Hは野生オオムギから誘導した変異体の対応する器官組織の観察像。(文献1) |
|
本研究グループはゲノム情報、遺伝学的解析および分子生物学的な証明を組み合わせて、2つの遺伝子を単離してDNA配列を決定しました。
それは196アミノ酸および202アミノ酸からなる蛋白質をコードする、いずれも全く新規な遺伝子でした。2つの遺伝子の進化を探るため、オオムギが持つ本遺伝子と、オオムギやコムギ、イネなどイネ科植物が持つ類似の遺伝子を比較。オオムギでは本遺伝子がセットで2倍(合計4つ)になっており、さらにそのうち1セットでは塩基配列がわずかに変化し、二つの膜貫通ドメインなど新たな機能を持つ蛋白質を作ることを発見しました。コムギも同じ機能の遺伝子を持つことから、本遺伝子の重複と機能進化はムギ類に特有で、ムギ類が Brachypodium と分岐して以降に起きたことが分かりました。 |
岡山大学では60年以上前に、野生オオムギの実が落ちることに関わる2つの遺伝子Btr1とBtr2の存在を研究し、それらが野生オオムギの自生地の西と東で集められた栽培オオムギ品種で異なっていることを発見しました。つまり世界中のオオムギ品種は大きく2つのグループに分類されることを明らかにしました。しかし、現在私たちが利用しているオオムギがどこで、どのようにして生まれたかは分かっていませんでした。
今回、本研究グループは529系統の野生オオムギと274品種の栽培オオムギについて、2つの遺伝子のDNA配列の変化を比較。その結果、栽培オオムギが祖先となった野生オオムギから、二回栽培化されたことを明らかにしました。最初は南レバント(イスラエル)でBtr1がbtr1へ突然変異し(図3A)、その後、北レバント(北西シリアから南東トルコ)でBtr2がbtr2へ別の突然変異が起こったことを突き止めました(図3B)。現在、栽培オオムギの品種は大きく2つのグループに分類されており、両突然変異の子孫を利用して、“人類最古の農業”が始まったことが明らかになりました。
Haberer and Mayer (2015) によるFeature articleもわかり易いですので時間のない方にお勧めします(図4)。 |
| |
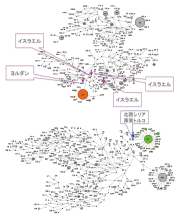
図3.栽培オオムギの起源地の推定。
(A)野生オオムギが南レバントでbtr1突然変異し現在の欧州等(西)の栽培オオムギ(赤色)が起源した。(B)野生オオムギが北レバントでbtr2突然変異し現在の日本等(東)の栽培オオムギ(緑色)が起源した。(文献1)を改変 |
|
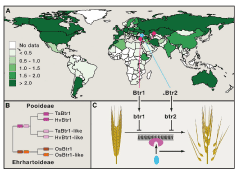
図4. オオムギは世界で4番目の重要作物
(A) 国別オオムギ生産量(2013 単位百万トン FAOSTAT)(文献1)。 オオムギは南レバントで小穂非脱落性遺伝子btr1により、北レバントでは小穂非脱落性遺伝子btr2により栽培化された事を明らかにした。 (B) Pooideae(オオムギを含む)はBtr1の重複と機能分化によって麦類に固有な種子脱落機構を獲得した。Ehrhartoideae(イネを含む)ではこのような進化が生じなかった(この模式図には描かれているが)。Btr2も同様の遺伝子進化を遂げた。(C)Btr1はレセプターをBtr2はリガンドをコードするという仮説が提案された(文献2)。 |
|
| |
文献1 |
| |
Pourkheirandish et al. (2015) Evolution of the grain dispersal system in barley. Cell 162, 527–539. |
| |
文献2 |
| |
Haberer and Mayer (2015) Barley: From Brittle to Stable Harvest. Cell 162, 469-471. |