NBRP ニホンザルの将来展望と最近の研究成果
伊佐 正 (自然科学研究機構 生理学研究所 教授)
 最近の研究から:
ウイルスベクター2重感染法を用いた経路選択的・可逆的伝達阻害法をマカクザルで確立、行動制御に成功 最近の研究から:
ウイルスベクター2重感染法を用いた経路選択的・可逆的伝達阻害法をマカクザルで確立、行動制御に成功
(Kinoshita et al. (2012) Genetic dissection of the circuit for hand dexterity in primates. Nature 487: 235-238.)
ヒトを含めた高等な霊長類は、手を巧みに動かす能力を身につけたことで、爆発的な進化を遂げたとされています。このように手指を一本ずつ器用に動かす能力は、大脳皮質の運動野が、筋肉を支配している脊髄の運動神経細胞に直接接続するようになったからと考えられてきました。一方で、ネコやネズミといった、より手の発達が原初的で不器用な動物では、大脳皮質からの指令は脊髄の介在ニューロンを介して間接的にしか運動神経細胞につながっていません。このような“間接経路”は我々霊長類にも残っていますが、何をしているのかはよくわかっていませんでした。このように進化の過程で残された“古い回路”が高等動物の脳でも使われているのか?それとも邪魔だから抑制されているのかについては、多くの議論がありましたが決着はついていませんでした。
今回、自然科学研究機構・生理学研究所の伊佐正教授・木下正治特任助教らと福島県立医大の小林和人教授・京都大学の渡邉大教授らの共同研究チームは、新しい二種類のウイルスベクターを組み合わせることで、特定の経路選択的に遺伝子を導入する方法(二重遺伝子導入法)を新たに開発し、この間接路を中継する脊髄介在ニューロン系(脊髄固有ニューロン:propriospinal neuron)を選択的に抑制することに成功しました(図1)。
すると、手指の巧緻運動は抑制開始後2日目に明確に障碍を受けることがわかりました(図2)。(ただし、他の経路による機能代償が速やかに起こり、5日目にはほぼ回復します。)これにより“間接経路”が、実は手指の巧みな動きを作りだすことに重要な役割を果たしていることが明らかになり、長年の論争に決着がつきました。
|
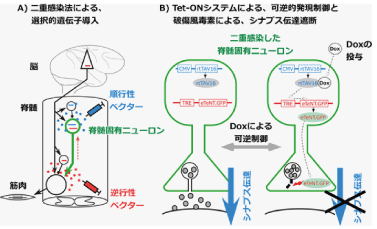
図1.脊髄固有ニューロン選択的なシナプス伝達の遮断
A) 脊髄固有ニューロンの投射先に逆行性ベクターHiRet-TRE-eTeNT-EGFPを注入し、細胞体がある中部頸髄の中間帯に順行性ベクタAAV2-CMV-rtTAV16を注入することで、脊髄固有ニューロンに選択的にウィルスを二重感染させた。
B) 二重感染しただけでは何も起きないが(左)、ドキシサイクリン(Dox)をサルが飲んでいる間のみ、Tetシステムによって破傷風毒素が発現し、シナプス伝達を遮断する(右)。 |
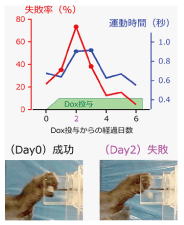
図2. ドキシサイクリンを飲んでいる間の前肢巧緻運動の障害
(グラフ)Dox投与後2日目に運動時間が延長し、失敗率が増加し、2日間続いた。
(写真)Dox投与前は、人差し指と親指を対向させた精密把持により餌をつまめているが、投与2日目では、うまく対向させることができず精密把持に失敗している。 |
今回の研究で鍵となったのは、2種類の新しいウイルスベクターを組み合わせて、特定の神経回路を選択的・可逆的に遮断する技術の開発に成功したことです。
これまで生殖細胞での遺伝子改変が可能だったマウスでは、このような操作は可能でしたが、霊長類では不可能でした。今回開発された方法は、マウスなどのように遺伝子改変動物の作製をすることが困難であった動物種においても、神経回路の選択的操作を可能にしたという点で、国際的にも注目されています。尚、本研究の成果により、伊佐、渡邉、小林の3名は平成25年度の文部科学大臣表彰(科学技術部門)を受賞しました。 |