第3期NBRPがスタート
第3期ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)が始まりました。トマトは、中核機関・筑波大学(代表:江面浩)、分担機関・大阪府立大学(代表:青木考)、バックアップ機関・岡山大学(代表:久保康隆)及び東北大学(代表:金山喜則)の体制で実施し、筑波大学及び岡山大学が個体レベルリソース、大阪府立大学及び東北大学がDNAレベルリソースを担当します。今期は、リソースの質の向上を目標に掲げています。現在までに収集整備した形態変異体に新たに果実成分データを付加します。果実成分は、果実の重要形質であり、そのため研究者コミュニティーの要望の多い形質です。これらの情報付加ができれば、リソース利用の一層の促進が期待されます。
マイクロトムの利用増加
トマトNBRPは、矮性小型品種マイクロトム(Micro-Tom)を基盤として、変異誘発系統、個別変異体及び完全長cDNAクローン、BACクローンの整備に取り組んできました。更に、NBRP事業の中でBACエンドシークエンス及びマイクロトムの全ゲノム配列解読に取り組み、これらの情報を順次公表しています。この間、トマト研究者コミュニティーでは、NBRPリソースを効果的に利用するためのTILLING∗1プラットホームの構築や、トマトを実験植物として利用するための形質転換体作成の支援(理研植物形質転換ネットワーク)、新たなリソースとしての、トマトFOX∗2変異誘発系統開発などが行われています。トマトNBRPは2007年に開始し、リソース及び関連情報の提供を行ってきました。その結果、マイクロトムを材料とした研究が世界的に活発になり、特に、2009年以降顕著で、マイクロトムを使った論文数、被引用数とも飛躍的な増加を示しています(トムソンロイター・ Web of Science)。
リソースを使った研究事例
トマトNBRPリソースを活用した果実重要形質研究の事例を2つ紹介します。1つめは、日持ち性形質の研究です(図1)。果実の日持ち性が短いと、生産、流通、消費の各段階で多くの果実が消費されずに廃棄されてしまいます。そのため、果実の日持ち性を向上させる研究が果実研究の重要テーマとして取り組まれています。NBRPリソースを最大限活用し、トマト重要形質制御遺伝子を見つけ出すTILLING技術が開発され、果実の日持ちを制御する新規遺伝子変異が見つかりました。この遺伝子(変異)があると、収穫果実を室温で2ヶ月以上保存できます。今後、トマトの日持ちを制御する有用遺伝子として利用されることが期待されます。2つめは、果実の着果性の研究です(図2)。
周年栽培が行われるトマトは、着果性が収穫量を決定する重要な形質です。トマトの周年栽培では、冬期と夏期に花粉発達の異常により、着果率が低下し、収量減の大きな要因となっています。そのため、花粉がなくても着果する性質、単為結果性は重要な形質で、精力的に研究が行われています。トマトNBRPリソースの中から単為結果性変異体が選抜され、その原因遺伝子の研究が進んでいます。今後、単為結果∗3の分子機構が明らかにされ、その制御技術の開発が期待されています。

図1:マイクロトムの日持ち性変異体の選抜と育種素材としての性能評価
A: 新規遺伝子から作られるタンパク質の一次構造と変異の位置
B : 変異体(Sletr1-2)と原系統(WT)の日持ち性の比較
C: 変異体(上段)と育種系統(下段)とのF1系統果実の日持ち性比較
|
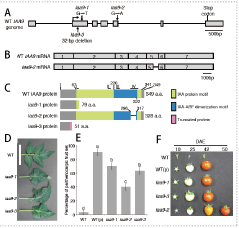
図2:マクロトムの単為結果性変異体の選抜
A, B, C: 変異体(iaa9-1, -2, -3)のIAA9遺伝子変異
D: 変異体の葉の形態、E, F:変異体の着果性 |
ゲノム解読で益々ホットに
本年、国際コンソーシアムによりトマト詳細全ゲノム解読情報が公表され、この情報を基にリシークエンスを行ったマイクトロトム全ゲノム解読情報も直に公表されます。現在、これらの情報と次世代シークエンサーを組み合わせたトマト変異体の解析が行われており、重要形質に係わる遺伝子が次々に解明される見込みです。新しい植物育種技術として注目されている、人工ヌクレアーゼ∗4を活用したゲノム編集技術の開発もトマトで始まっています。トマトを研究材料とした研究が益々ホットになってきました。
|
| ∗1
| Targeting Induced Local Lesions IN Genomesのことで、ゲノムや遺伝子上の遺伝子置換を検出する方法。塩基対を形成できない変異点を特異的に切断する事により、野生型と異なる塩基の位置を知る方法である。 |
| ∗2
| FOXはFull-length cDNA Over-eXpressingのこと。目的の遺伝子を過剰に発現させることによって生じる変異。 |
| ∗3
| 受精が行われずに子房壁や花床が肥大して果実を形成すること。果実は通常種なしである。 |
| ∗4
| DNA に特異的に結合するドメインと、DNA 切断ドメインを連結させたキメラタンパク質で、Zinc-Finger Nuclease(ZFN),Transcription Activator-Like Effector Nuclease (TALEN)などが使われている。2つの人工ヌクレアーゼが近接する標的配列に結合するとDNA 切断ドメインが2量体となりDNA を切断する。切断されたDNA は、相同組換えあるいは非相同末端連結により修復されるが、この時に目的の遺伝子を改変することが可能となる。 |