ショウジョウバエ遺伝資源センター
10年の歩み <後編>
~これまでの10年からみた今後の10年~
京都工芸繊維大学 ショウジョウバエ遺伝資源センター
センター長 山本 雅敏
これまでの10年をふりかえって
ショウジョウバエ遺伝資源センターが、京都工芸繊維大学に、文部省令施設として設置された事は、10年を経過した今でもミステリアスな事柄として、必ず質問のひとつにあげられる。確かに、ショウジョウバエは、工芸でも、繊維でもないことから、京都工芸繊維大学とマッチしない。そんな
”そぐわない”生き物が、国立大学の研究施設で維持され、しかも世界で最大のショウジョウバエの飼育維持および研究施設であり、飼育匹数は約15,000,000匹だというと、より一層ミステリアスさが増幅されるようである。 |
2010年7月の時点で、系統数は26,000である。一つの系統は飼育瓶3本で飼育されており、もう一つは、飼育瓶2本で維持されている。 全ての系統は2つの飼育室に隔離して維持されており、 火災や地震などで一斉に損失することの無いように安定維持第一で、飼育維持されている。一本の飼育瓶には平均約100匹の成虫がいるので、26,000系統×5本×100匹/本として、総数約13,000,000匹のショウジョウバエがいる。これ以外に、センターの研究用として2,000,000匹は飼育している。これらのほとんどは純系で、遺伝的にも管理された重要な研究用ショウジョウバエ突然変異体系統である。さらに重要な系統は、ショウジョウバエ遺伝資源センターとアメリカの系統センターで、二重に維持している。(写真1)。 |

写真1:飼育状態 3本飼育(左)
|
センター誕生のルーツは、京都工芸繊維大学繊維学部応用生物学科遺伝学研究分野(後に染色体工学研究分野に名称変更)の私の実験室兼飼育室である。それ以前に、渡辺隆夫先生が国立遺伝学研究所から移る事があれば、ショウジョウバエだけの研究者で構成される研究室を作りましょう、と話しをしていた。当時、ショウジョウバエ研究者だけで構成されている研究室は、都立大以外に無かった。 |

ショウジョウバエ遺伝資源センター
センター棟 |
二人で描いた共通目標が京都工芸繊維大学で実現できる、という見通しから合流したのは、1993年の事であった。この背景には、京都工芸繊維大学はカイコが主流であり、より良い品種の改良・開発などを育種だけではなく、遺伝学的あるいは遺伝子組換え技術等を応用して発展させる、という目的があったと聞いている。遺伝子関連技術といえば、その代表的生物であるショウジョウバエを用いて、カイコの育種等に向けた先端的研究を進めるのが狙いであったと聞き、そのように説明している。大学が、このように明確な理由を持って、各研究室の人事が進められているのかどうかは不明であるが、以上が全体的流れとしての背景とショウジョウバエの研究室が京都工芸繊維大学に生まれた発端である。 |
その1年後、概算要求という私にとって全く未知の扉を押し開けることになった。この経緯はここでは記さないが、縁あって、これ以上は望めないほどの最良な人々との出会いや巡り会いがあり、ショウジョウバエ遺伝資源センターが設立されることとなった。むちゃくちゃ大変だった。同じ事は2度と出来ないだろう。しかし、苦しみの中に、何が何でも絶対に作ってやる、という執念に似た熱意が生まれた事が思い出される。
研究も一切出来ず、たった一人でセンターの組織(教授、助教授、助手(振替)、非常勤研究員、研究補佐員)と運営費、センター棟の建設、特別設備、外国人研究員(客員3種)、その後の分割予算と関連経費など、の申請を行なって来た。センター設立を手伝ってもらえる人も無いなか、多くの学生や同僚に迷惑をおかけした。このことにすごく悔いが残っている。(写真2) |
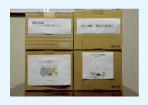
写真2:概算要求に作成した
資料(一部)
|
1990年以前は、系統保存費として僅かな経費がいくつかの研究機関に配分されていた。ショウジョウバエの場合は、国立遺伝学研究所、大阪大学、長崎大学に配分されており、東京都から東京都立大学に配分されていた。これは現在も続いている。しかし、ストックセンターとは名ばかりの小さな規模であった。
その当時アメリカ合衆国には、カリフォルニア工科大学とボーリンググリーン州立大学にストックセンターがあり、ヨーロッパにはスウェーデンのウメオ大学に個人研究室から発展させた系統センターがあり、国際的研究支援基盤となっていた。その後、アメリカのストックセンターはThom Kaufmanの移動とともに、インディアナ大学に移る事となる。ちょうどこの頃、ショウジョウバエが発生の基本となるホメオボックスの研究で有名になり、ショウジョウバエの重要性が広く認識されるようになった。さらに、急激なゲノム研究の発展と転移因子(Pエレメント)を形質転換ベクターとして利用した膨大な研究成果が世に出ることによって、系統センターの重要性が再認識されるようになった。 |
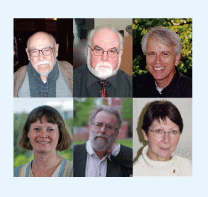
写真3:(写真左上から)アメリカのMel Green, Thom Kaufman, Chuck Langley,(2列目左から)スウェーデンの Asa Rasmuson-Lestander, イギリスの Michael Ashburner, フランスの Marie-Louise Cariou |
ちょうどそんな時に、当時の文部省に「ショウジョウバエ遺伝資源センター」の設立要求を提出したいと考えていた。アメリカやヨーロッパも、ショウジョウバエの系統保存施設の安定と拡張は悲願であり、インディアナ大学の系統センターも予算申請に非常に大きな努力を払い、専任スタッフの確保とセンターが使用する部屋数を増やして行くことを目指していた。日本でストックセンターを設立しようと考えているとの情報は非常良い感触で迎えられ、特に、アメリカのMel Green, Thom Kaufman, Chuck Langley, スウェーデンの Asa Rasmuson-Lestander, イギリスのMichael Ashburner, フランスのMarie-Louise Cariou (写真3)他から、「協力を惜しまない、必要なら何の応援でもする」などの支援を得たが、「なぜそんな大変な事をするんだ」との、友情のコメントも多かった。
最近の概算要求とは全く異なる、二度とやりたくない試練の時期を経過し、1998年12月に文部省令施設「ショウジョウバエ遺伝資源センター」設置の内定を得た。あの努力をして当然の事だとその時は思ったが、本当に大変なのは、この後に続くセンターの運営、ならびに同時進行の概算要求の連続だったが、紙面の都合で省略する。 |
|
今後の10年について
諸外国との連携
20世紀末にゲノム配列が明らかにされ、多くの生物のゲノム情報がごく短期間で決定され、すぐさま公開されるようになったとき、ショウジョウバエを用いた研究のあり方が大きく変わると感じた。これまでのゲノムをひとつの機能単位として考える考え方から、遺伝子の集積として考える方向に変化し、遺伝子単位の機能解析に研究がシフトする。遺伝子の研究という事であれば、ショウジョウバエを用いる利点が何であるかを再度考え直さなければならない。DNAの普遍性から大きな生物を研究材料として遺伝学研究ができるメリットを考えると、 基礎的研究成果は豊富だがショウジョウバエの優位性は劣る。 |
そのような中で、ショウジョウバエの研究者はトランスポゾンを形質転換ベクターとして、挿入による遺伝子破壊、各種遺伝子や変異遺伝子の導入、組換え標的配列の挿入、蛍光タンパクとの融合遺伝子の導入、など多様なDNA断片や機能単位が導入された系統を作成した。それらは、すべてショウジョウバエの全ゲノムに分散挿入する系統である事から、研究目的遺伝子以外の系統が派生的に作成されることとなり、派生系統の殆どを無駄にする事なく、ストックセンターから研究者に提供されるシステムが出来上がってきた。ゲノムサイズが小さく、ゲノム配列情報は、詳細かつ正確であり、唾線染色体地図による遺伝子座の決定が容易であるという、ショウジョウバエの利点が発揮された。 |
 |
|
研究は全世界で行われている。各研究室で、将来誰かにとって非常に有用な系統が研究の副産物として生まれている可能性がある。それらの遺伝資源を研究費申請者が研究目的にだけ使用して、その後継続して維持するための手段や予算がないことから廃棄されるとすれば、研究費の非常に無駄な使い方となる。副産物として作成された膨大な系統の中から、mutant miningとでも呼べるようなスクリーニングに供する合理性が考えられるべきである。
この点について、いくつかの国際的研究ファンドはすでに研究費申請の段階で、申請研究の終了後、作成された遺伝資源の継続維持の可能性を確認するため、系統維持計画と維持機関の確認書類の提出を、要求している。
このような経緯から、EUから多くの系統の譲渡を受け、それが国際的資産となっている。今後、国内の研究費申請段階においても、研究成果物の取扱に関する事前計画と受入れ機関並びに受入れ計画などの提出を考慮されるべきである。生物資源の維持コストの低減と、継続性の高い重要遺伝資源の維持に向けた、研究者間の共通認識として理解されるべきである。この種の生物遺伝資源については、国際的学術資源として公平なアクセスと利益を享受できる体制が必要である。 |
それにしても増加の一途をたどる系統数に対応するために、「系統の選択」と「保存技術と経費削減」は別プロジェクトとして、両立させなければならない重要課題である。特に近い将来のプロテオミクス研究にとって遺伝的背景が均一な系統は必須である。また、遺伝子組換え技術で培われた各種標識・観察技術を、 大きなゲノムを持つ生物(バッタ・ツユクサ・ユリなど)に応用し、細胞分裂時や減数分裂における染色体の分離・分配や、細胞内器官の分裂機構、また各種生物のクロマチン削減を再び細胞学的観察研究で詳細に検討する時代が来るのではないかと思われる(写真4)。
そのような時代に備えた各種遺伝子の変異体の収集・維持は、非常に重要な遺伝資源となるであろう。基礎的研究に使用する生物資源は、現段階でどれが重要で、どれは不要であるかを判断するのは不可能に近い。そのためにも、新しい系統保存技術は今後10年の最重要課題である。■ |
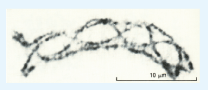
写真4:減数分裂
|