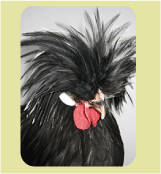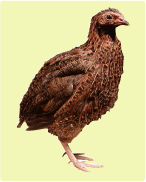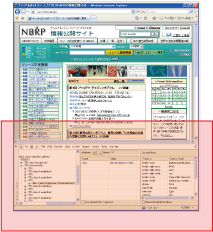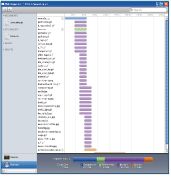1. ニワトリの重要性 1. ニワトリの重要性
ニワトリは紀元前5,400年頃にアジアの赤色野鶏
(Gallus gallus)を家畜化したことに起源を発し、食料資源としても重要かつ身近な存在です。 鳥類は進化上、 哺乳類と他の脊椎動物を橋渡しする重要な存在で、特にニワトリは現存する約9,600種の鳥類の代表的モデル生物です。これまで、がん、ウイルス、免疫、発生、神経科学などの研究分野や、ワクチンや医薬品の生産にも利用され、 多大な貢献してきました。我が国における実験動物としてのニワトリ利用数は胚を除いてもマウスの1/20、ラットの1/2以上の規模を誇っています。
 2. ニワトリ遺伝資源の現状 2. ニワトリ遺伝資源の現状
2004年のニワトリゲノム解読により遺伝資源としてのニワトリの重要性はさらに増していますが、諸外国では研究予算の削減によって鳥類バイオリソースが次々と姿を消しています。鳥類遺伝資源対策委員会(AGRTF)によると、1984年から1998年の間にアメリカとカナダにおいて268系統のニワトリが消失したことが報告されており、その後もその流れに歯止めがかかってません。鳥類においては胚の凍結保存技術が確立されていないため、生きたコレクションとして維持する必要があることもその流れに拍車をかけています。したがって我が国のニワトリ資源の保存と供給には大きな期待が寄せられています。
しかし試験・研究用のニワトリの大部分は商品(複数種鶏の多元交配から生産されるヘテロ性の極めて高い個体)からの転用であり,遺伝的に標準化された系統の占める割合は極めて低いのが現状です。
 3. センターのミッション 3. センターのミッション
生命農学研究科では、愛知県の家禽産業への貢献を重視して、1952年以来、文部省事業「野鶏・家鶏系統保存事業」を継続してきました。この歴史をふまえ、平成19年度から文科省特別教育研究経費(研究推進)「鳥類生命科学におけるポスト・ゲノム研究の展開-鳥類遺伝資源の多様性維持・開発と高次機能研究への活用-」がスタートしたのに伴って、当センターは発足しました。
当センターでは30年以上にわたり、多型マーカーをホモ化する方法で高度に近交化を図った10系統を含む18系統のニワトリを維持しており、遺伝資源と研究情報の提供に努めています。国際的に認められた近交系や高度近交化系統は本センター以外には少ないのに対して、ニワトリ標準化系統の利用を期待している研究者の潜在数は極めて大きいといえます。 試料提供数も年々増加しており、2007年度実績は4,885個体(所属機関外41%、3,546個体が近交化系統)となっています。今後もこの活動をさらに加速させ、我が国の鳥類研究者コミュニティの形成と鳥類研究の発展に貢献したいと考えています。
|