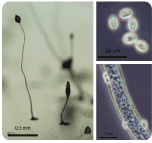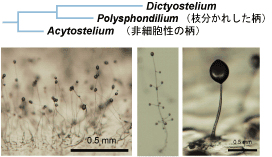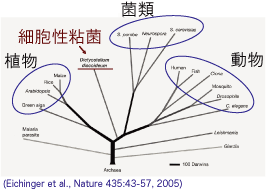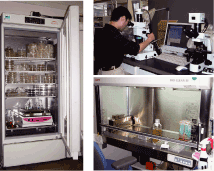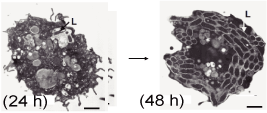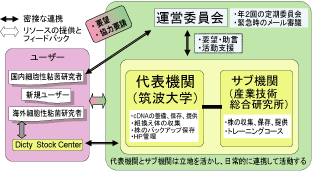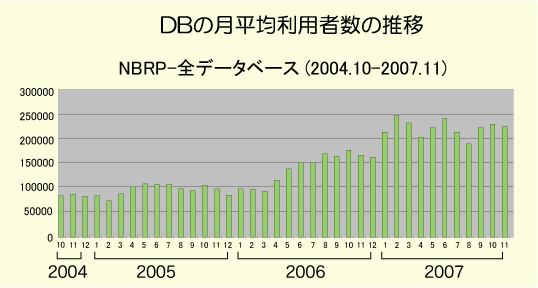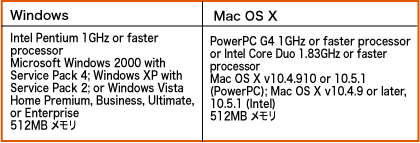作成したアプリには air という拡張子が付き、 AIR(Adobe Integrated Runtime) がインストールされた環境で実行することができます。 airは以下の環境で実行できます。
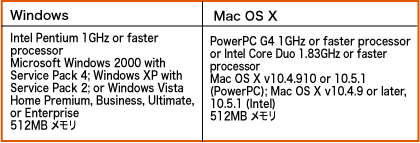
アプリ作成者は実行環境である AIR と airアプリ を同時にインストールできるシームレスインストールという方法をユーザに提供することができます。(ただしこの方法はブラウザの種類やバージョンによっては動作しない場合があります。)
■ シームレスインストールはこちらから
http://www.shigen.nig.ac.jp/shigen/news/n_letter/2008/3/index.html
※ シームレスインストール が上手くいかなかった方は以下から個別にダウンロードしてインストールして下さい。 インストールの順番は「AIR」、「sample.air」 の順です。
(sample.airをダウンロードした際にファイル名が ”sample.zip“ となってしまった場合は ”sample.air” に変更して下さい。)
■ AIR(airアプリを実行するためのソフト)
http://labs.adobe.com/downloads/air.html
■ sample.air(今回作成したairアプリ):
http://www.shigen.nig.ac.jp/shigen/news/n_letter/2008/3/sample.air
Adobeのサイト(http://www.adobe.com/jp/devnet/air/gallery/)では様々なAIRアプリがダウンロード可能です。
AIRコンテスト(http://www.adobe.com/jp/special/air/contest/)も開催されているので自分で作成したAIRアプリを投稿してみてはいかがでしょうか。
(坂庭 真悟)
|


 [細胞性粘菌とは]
[細胞性粘菌とは]